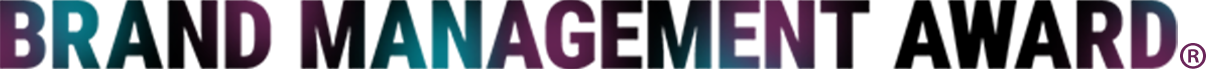REPORT開催レポート
第11回公開シンポジウム
- 開催日
- 2023年11月3日(祝)13:00‐17:30
- 場所
- 有楽町朝日ホール
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、2023 年 11 月 3 日、有楽町朝日ホールにて、第 11 回公開シンポジウムを開催しました。会場約 400 名、オンライン約 200 名、計約 600 名の方に参加していただいた今回のシンポジウムでは、「ブランディングで日本を元気に!ブランディングが創り出す社会を良くする絆とデジタル化の可能性」と題し、基調講演やコンテストで選ばれた実践事例の発表、授賞式などを行いました。
開会の挨拶
最初に代表理事の岩本俊幸氏が次のように挨拶しました。

「本日は、第 11 回公開シンポジウムにご参加いただきありがとうございます。当協会は、ブランド価値向上を担う人材育成の専門機関として、設立当初より 3 つの基幹講座を開講し、『ブランディングで社会課題解決する実践コミュニティを築く』というビジョン、『ブランド・マネージャーを数多く輩出して企業価値を向上し、日本経済発展に貢献する』というミッションのもと、『ブランディングで日本を元気にする実践コミュニティ』を目指しております。
協会は 2010 年に一般財団法人格を取得し、通常の講座はもとより、産学官連携によるイベント、セミナー、勉強会なども数多く実施してきました。中でもシンポジウムは 2010 年から開催しており、コロナ禍で開催できなかった 2 年間を除いて毎年開催し、今回が 11 回目になります。
協会資格者によるブランディング事例はこれらの受賞企業以外にもたくさんあり、着実に増え続けています。このような成果を上げる実践事例が多くあるということは、協会で提供するカリキュラムが単なる机上の道具ではなく、現場で活用できるもので、再現性の実証がなされているのではないかと回を重ねるごとに強く感じております。これらの成果は、資格者の皆様の努力の賜物であり、関係者の皆様のご支援に改めて感謝を申し上げます」
基調講演「デジタル時代にブランドはこう変わる」
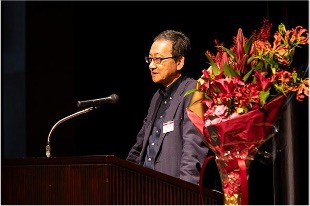
基調講演では、当協会特別顧問を務める中央大学名誉教授の田中洋氏が「デジタル時代にブランドはこう変わる」をテーマに講演しました。 田中氏は、ブランドにとってこれまでがどのような時代だったかを振り返り、これからのブランドがどう変わっていくべきか、3 つのポイントを挙げて解説しました。
田中氏は、20 世紀のブランド戦略の例として、カウボーイを広告キャラクターに起用した Marlboro の広告や、デイヴィッド・オグルヴィのハサウェイシャツの広告、ウディ・アレンを起用した西武百貨店の広告などを紹介。これらの例から、20 世紀のブランド戦略の本質は、関係のないもの同士を結び付けるなどメタファーを鍵にしたものであったと指摘。
差別化のない商品をブランド・イメージによって差別化する時代であったと解説しました。
そうした前提を踏まえ、田中氏はこれからのブランド戦略が向かうべき変化として、「経験化」「信号化」「理念化」という 3 つの方向性を紹介しました。
「経験化」では、Google や Microsoft などの IT プラットフォーマーやオンライン会議ソフトの「Zoom」、ライザップのジム「chocoZAP」などを例に挙げ、デジタル時代の現在は、ブランド・イメージの時代とは異なりブランドの経験そのものが重要であり、「いかに顧客の経験をデザインできるか」が大事であると指摘しました。
次に「信号化」では、「Yakult(ヤクルト)1000」の例を紹介し、同商品が明快なベネフィットを謳っている点に着目。ほかにユニクロの大ヒットしたバッグや Zoom なども例として挙げつつ、デジタル時代には「ブランドがある面では信号化、つまり非常に単純な意味だけを持って我々の前に登場するのではないか」と見解を述べました。
さらに「理念化」について、顧客はブランドの理念・哲学・考え方を考慮して購買を行うことなどを解説し、オーガニックワインやヘアケア商品の「ボタニスト」などの例を紹介。ブランドの背景にある「理念」が購買の大きな引き金になっていると説明したうえで、「デジタル化時代に『ブランドの理念化』が進行すると、そのブランドがどのような理念・考え方で動いているかを鮮明にすることが求められる」と指摘しました。 最後に田中氏は、今後のブランド戦略の方向性について言及。ブランド・イメージの時代だった 20 世紀から、今後は経験化、信号化、理念化という方向にブランドが向かっていくことを予測し、講演を締めくくりました。
協会フレームワークのご案内

次に、同協会本部トレーナーの榎本真弓氏が「一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会の『ブランド戦略』および『ブランド構築の 8 ステップ』の概要」と題して講演しました。
榎本氏は、まず協会が提唱しているブランド戦略の概要について解説。協会が体系化した「ブランド戦略ピラミッド」を紹介し、経営理念や経営戦略、マーケティング戦略、コミュニケーション戦略についてそれぞれ解説しました。
次に、榎本氏は「ブランド戦略の 8 ステップ」の概要を紹介。ステップ 1 からステップ 8 までそれぞれの内容を詳細に解説したうえで、ブランド戦略は大人数で長期的に行われるため、このステップをブランド・ステートメントに明文化して関わるメンバーで共有し、検証しながら進めていくことが必要だと話しました。 続けて榎本氏は、このステップの特徴として、ブランド・アイデンティティを境に前半と後半で分かれることを説明。前半が「ブランド・アイデンティティ形成ステージ」、後半が具体的なブランディング活動を決める「目標設定ステージ」であることを解説しました。
ブランディング事例コンテスト~事例紹介~
今年で 9 回目となるブランディング事例コンテストでは、当協会で学んだことを現場で活用した事例を募集し、その中から構築プロセスと成果が優れた事例を表彰しています。シンポジウムでは、書類審査とオンライン審査を通過した 9 名が登壇。第一部、第二部の二部構成で最終審査となる事例プレゼンテーションが行われました。(受賞事例は「ブランディング事例コンテスト~審査発表・授賞式~」に記載)
ブランディング事例コンテスト~審査発表・授賞式~
今回発表された事例の中から、2023 年は以下の企業に各賞が贈られました。大賞、準大賞は、前回コンテストと同様、参加者による全員投票で決定しました。(審査員コメントは「審査員コメント」に記載)
・大賞:私立男子高校のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 OICHOC 八幡清信氏 プロジェクト名:&Branding
(針谷誠児氏))
・準大賞:「Air ビジネスツールズ」のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社リクルート 野村恭子氏)
・最優秀賞:私立男子高校のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 OICHOC 八幡清信氏 プロジェクト名:&Branding
(針谷誠児氏))
・最優秀賞:「Air ビジネスツールズ」のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社リクルート 野村恭子氏)
・優秀賞:サステナブルなスイーツづくりのブランディング
(ブランド・マネージャー:有限会社 TTDESIGN 坪田有希子氏)
・優秀賞:「TEMAHIMAN」のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 doushi 清水章充氏)
・中小企業庁長官賞:地方の税理士事務所のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社コムデザインラボ 高木純氏)
・地方創生審査員特別賞:持続可能な地域ブランディング
(ブランド・マネージャー:合同会社 Brand.Communication.Design. 平野朋子氏 プロジェクト名:本巣市ブランドアンバサダー会議)
・地方創生審査員特別賞:稲庭うどんのブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社ビスポーク 長田敏希氏 プロジェクト名:チーム稲庭うどん小川)
・SDGs 審査員特別賞:ラグビーを通じて地域を元気にするブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社ファーストデコ 扇野睦巳氏)
・SDGs 審査員特別賞:「ZANPUP/ザンプアップ」のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 Raymaka 末宗千登世氏)
このほか、以下の企業が特別奨励賞、奨励賞を受賞しました。
・特別奨励賞:仕組みづくりアプリケーションのブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社サルカン 佐藤慶臣氏)・奨励賞:会社を進化させていく採用ブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社テングッド 名引佑季氏)
・奨励賞:ゼノアックのブランディング
(ブランド・マネージャー:日本全薬工業株式会社 小川雅史氏)
・奨励賞:「渋谷 Web3 大学」のブランディング
(ブランド・マネージャー:シマウマ合同会社 北村元氏)
・奨励賞:「セントルマルシェ」のブランディング
(ブランド・マネージャー:合同会社 CONTACT(アトリエ宙と廷) 清水早苗氏) 大賞、準大賞の発表の要旨は以下の通りです。
大賞 私立男子高校のブランディング
「私立男子高校のブランディング」は、創立 120 年以上の歴史のある男子校・正則学園高校のブランディングの事例です。同校は教員によるストライキが多くのメディアで過熱報道された結果、イメージが低下。信頼を取り戻してより魅力的な学校に生まれ変わるため、新校長のもとでブランディングチームが発足されました。
ブランディング開始時の正則学園の状況は、学力レベルが偏差値 47 程度で受験生の過半数が滑り止めとして受験しており、約 30 年間定員割れが続いていました。また、体育会系色が強いため心理的ハードルが高いことや、ストライキが起きたことへの不安などの課題も抱えていました。ただ、正則学園にはいじめを許さない校風や男子だけの気楽な学校生活、生徒の不安な気持ちに寄り添える安心な環境などの魅力もありました。そこで、ペルソナを「友達づくりが苦手で、勉強や学校生活に不安を抱えている隠れ不登校の男子受験生」に設定。ブランド・アイデンティティは「安堵できる環境で 友と共に成長し 個性を伸ばせる男子校」とし、タグラインは「繋がる『&』から伝わる『安堵』へ」に、ブランド名は「&
SEISOKUGAKUEN」と掲げました。
次に、安堵できるブランド体験の実現のためには「男子校イコール男らしく育てる場所」という思い込みを外す必要があると考え、学校イメージは文科系にフォーカス。教育方針は「男らしくではなく、自分らしく」と多様性を尊重し、花をいける男子をメーンとした広告戦略を展開。キャッチコピーは「いつか花咲く君たちへ。咲く場所はここにある。」とし、花いけ男子部を筆頭に文化部にフォーカスしたキービジュアルを制作しました。デジタルブランディングではオンライン情報を充実させ、ウェブサイトもリニューアル。学校紹介動画は実在する部活、在校生、先生に出演してもらって制作。屋外広告では QR コードを活用してリアルとデジタルを繋ぎました。 こうしたブランディングの結果、ウェブサイトの PV 数は 25 万アップ。学校説明会の申し込み PV 数は 10 倍に跳ね上がりました。また、個別相談会の参加者数は 2020 年と 2023 年の比較では 218 パーセントアップ。入学者数は 142 パーセントアップして 250 名の定員を超え、約 30 年ぶりの快挙達成となりました。
準大賞 「Air ビジネスツールズ」のブランディング
「『Air ビジネスツールズ』のブランディング」は、数人のプロジェクトで始まった「Air レジ」から 330 万以上の事業者が利用するまでに成長した「Air ビジネスツールズ」というサービス群ブランドの事例です。
私は 10 年間、「どうすれば経営から投資を獲得し続けられるのか」「どうすれば従業員のブランドへの愛着を高め続けられるのか」「どうすればブランド・マネージャーとして必要とされ続けるのか」という 3 つの問いに向き合い続けました。その結果、試行錯誤でたどり着いた答えが「論理的に示し続けること」「情熱を持って伝え続けること」「信頼してもらう努力をし続けること」でした。
1 つ目の「論理的に示し続けること」では、投資決裁者からの「そこに投資したら売り上げが上がるのか」という一言がきっかけになり、2 年間かけてブランディングのビジネス貢献を定量化。2 つ目の「情熱を持って伝え続けること」では、ブランド・ステートメントを策定してストーリーにして伝え続けました。3 つ目の「信頼してもらう努力をし続けること」は、2017 年からオンラインでブランドレビューを開始。レビュー自体を意味あるものにするために現状を徹底的に可視化し、半期ごとに振り返りを実施。ブランドのバナーを制作している広告代理店にもブランド勉強会を実施するなどした結果、レビューは当たり前という文化が根付き、3190 件のブランドレビューが起票されました。 この「論理的に、情熱を持って、信頼してもらう努力をする」という法則は、ギリシャ時代の哲学者アリストテレスが人を動かすための三要素とした「ロゴス、パトス、エトス」と同じであり、ブランディングが普遍的な証拠だと思います。本日ご紹介した事例は 10 年間の試行錯誤の末に導き出したものですが、業種も規模もエリアも関係なくブランド・マネージャーの方に応用してもらえるとうれしいです。
審査員コメント
進行:高田敦史氏(当協会アドバイザー)
・大賞&最優秀賞「私立男子高校のブランディング」について<田中洋氏(当協会特別顧問、中央大学名誉教授)>
「普通なら共学化、系列化という方法でしのぐと思いますが、それをブランディングという手法で問題解決し、かつ結果も伴っているのが大変素晴らしく、ブランディングの力を改めて我々に見せつけてくれたと思います」
八塩圭子氏(当協会顧問、東洋学園大学現代経営学部教授)
「男子校はポジショニングが難しい時代だと思いますが、このような素晴らしいブランディングでみんなから支持され、高校生たちが生き生きとしている姿にすごく感動しました。そして『咲き誇れ』『芽吹いて』など、言葉が素敵で刺さります。私も大学でブランディングの難しさを日々痛感しているので、非常に参考になる素晴らしい事例だと思います」
山口夕妃子氏(当協会顧問・佐賀大学芸術地域デザイン学部教授)
「準大賞、大賞の事例は『Air』『安堵』などビジョンが伝わりやすく、すっと入ってくるうえに深みを持って伝わり、魅力がぐっと詰まっていると感じました」
・準大賞&最優秀賞「『Air ビジネスツールズ』のブランディング」について
田中洋氏(当協会特別顧問、中央大学名誉教授)
「ここ 40 年、小さな商店が潰れていく様などを見てきましたので、中小企業や職人の世界を助けている『Air ブランド』の受賞は、時代的にも意義のある賞だったのではないかと強く感じました」
八塩圭子氏(当協会顧問、東洋学園大学現代経営学部教授)
「ブランドの価値そのものをデータによって可視化したことが非常に大きかったと思います。また、ブランドマーケターの真髄とは何かということを、本日のプレゼンとお言葉で可視化してくださったと思います。そもそもブランドは、目に見えないものを創出して可視化する作業だと思いますので、その究極の姿を見たような気がしました」
・優秀賞「サステナブルなスイーツづくりのブランディング」について
榛沢明浩氏(当協会評議員)
「全体の流れが素晴らしく『こう進めるといいんだな』というお手本のような事例だと思いました。特にお客がブランドを体験する仕組みがしっかり埋め込まれているのが素晴らしく、これからもどんどんロイヤルティが上がっていくのではと期待しています」
水野与志朗氏(当協会評議員、水野与志朗事務所株式会社代表取締役社長)
「SDGs を前面に押し出してもなかなか受け入れてもらえないことを前提にして『可愛い、美味しい商品』という部分を入り口に持ってこられたことが非常に秀逸かつ戦略的な視点だと思います。商品を手に取った方がパッケージの裏側を見ると『あ、実は環境に優しいんだ』というメッセージがついている。この辺がとってもチャーミングだと思いました」
・優秀賞「『TEMAHIMAN』のブランディング」について
榛沢明浩氏(当協会評議員)
「非常に熱い人が何人も出てくるプレゼンで、清水さんご自身も含めて、ブランディングにはやはり熱いハートが大事だということがよく伝わってきました」
水野与志朗氏(当協会評議員、水野与志朗事務所株式会社代表取締役社長)
「情熱の部分が全体の 70 パーセントぐらいを占めているような印象のプレゼンだったと思います。“勢い”に乗ったときに会社がどう変わっていくのか。そんなお話を聞かせていただいたような気がします」
・中小企業庁長官賞「地方の税理士事務所のブランディング」について
島田良氏(当協会理事、株式会社りんごの木代表取締役社長)
「いち税理士事務所という枠を超えた、地域に大きく貢献するという地方のブランドのあり方として素晴らしい事例だったと思います。高木さんの関わり方も『地方を活性化させたい』というところに留まらず深堀りをして、整理してからスタートされたのが素晴らしいと
思いました。地方でのブランディングの可能性を感じさせる事例だったと思います」
山崎浩人氏(当協会アドバイザー、株式会社 CARTA COMMUNICATIONS ブランド・コンサルタント)
「税理士事務所は差別化自体が難しいというお話をされていましたが、差別化どころか枠を超えて多角化へ、というところが印象的でした。ブランドの核になる部分を押さえれば、枠を超えたり多角化したりということは可能だということを見事に証明していただいた事例だと思います」
・地方創生審査員特別賞「持続可能な地域ブランディング」について
田中洋氏(当協会特別顧問、中央大学名誉教授)
「地方の創生事例ということで、非常に印象深く聞かせていただきました。仕組みというものを中に取り入れられて、持続的で、予算が途切れてもなお続くところがすごくしぶとくて
『しぶといブランディング賞』を差し上げたいと思いました」
山崎浩人氏(当協会アドバイザー、株式会社 CARTA COMMUNICATIONS ブランド・コンサルタント)
「お話を聞いていて、3 つの大きなポイントがあるなと思いました。1 つは、通常のマーケティングでいうセグメンテーションをやってはならない、市民全体に届けなきゃいけないということで、属性ではなく価値観で訴求したこと。また、最初から市民を巻き込んだことも大きなポイント。もう 1 つは異動を前提として意識されたうえで設計したこと。この 3 つが大きなポイントだったと思います」
・地方創生審査員特別賞「稲庭うどんのブランディング」について
八塩圭子氏(当協会顧問、東洋学園大学現代経営学部教授)
「地方の小さなメーカーさんが国内のみならず世界でも存在感を増すことができる、それはブランディングの力で可能なんだ、と素晴らしい事例として聞かせていただきました。市場が縮小傾向にあることや、どのように世界に出ていけばいいんだろうということなど、同じような地方が抱える様々な課題は、この例を参考にすることで解決できるのではないかと感じました」
島田良氏(当協会理事、株式会社りんごの木代表取締役社長)
「製品のブランディングをフックにして、実は会社そのものを変えていこうという取り組みだと思います。クリエイティブが素晴らしいのはもちろんですが、最初の段階でポジションに関係なくみんなで一緒により良い製品を作っていくんだということに着目され、ビジネスの構造自体をブランディングによって変えていく取り組みをされたことにすごく価値があると思います」
・SDGs 審査員特別賞「ラグビーを通じて地域を元気にするブランディング」について
長崎秀俊氏(当協会顧問、目白大学社会学部教授)
「直接的な SDGs ではなく、ラグビーを媒介させることで違うイメージを生み出してわかりやすく伝える、という部分が非常に良かったと思います。ラグビー選手はインタビューの際、誰もが『チームのために』と言います。このような部分が自然とみんなから共感を得るわけですが、それを媒介に使われたのが非常に素晴らしいと思いました」
徐誠敏氏(当協会アドバイザー、名古屋経済大学経営学部准教授)
「迫力満点で感動的かつダイナミックなブランドストーリーだと感じました。SDGs の課題を解決することで、学生は情熱や積極性、協調性、コミュニケーションなどの非認知能力を高めることができ、同時にユニークな商品をビジネスに自然に結び付けることもできており、経済的価値だけではなく社会的な価値も同時に実現する意義の大きいプロジェクトだと思います」
・SDGs 審査員特別賞「『ZANPUP/ザンプアップ』のブランディング」について<小池玲子氏(当協会評議員、クリエイティブハウス R-3 代表)>
「『捨てるものを再利用』というのはよくある話ですが、目の付けどころが違うと感じました。再利用を感じさせないハイクオリティなブランド。再利用にありがちな寂しさを感じさせず、高級でありながら環境に配慮という、ハイインカムな知識層を満足させるコンセプト。
長い間アパレルで活躍してきたチームが作り出した新しい形の再生ブランドです」
山口夕妃子氏(当協会顧問・佐賀大学芸術地域デザイン学部教授)
「地域の中に残っている残布を使って環境問題を考えることなども含めて、日本から発信
していく魅力的なブランディングができているなと本当に感銘いたしました」
・特別奨励賞「仕組みづくりアプリケーションのブランディング」について
山口夕妃子氏(当協会顧問・佐賀大学芸術地域デザイン学部教授)
「インターフェースを見える化していく仕組みづくりにフォーカスした取り組みをされていて、今までにないインターフェースをしっかり作られていました。DX をブランディングの仕組みに入れていくところを高く評価させていただきました」
閉会の挨拶
最後に顧問の長崎秀俊氏から次のような閉会の挨拶がありました。
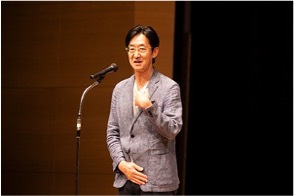
「会場の皆様、コンテストに出場された皆様、裏方で支えている協会の皆様、審査員の皆様、本日はどうもありがとうございました。大人数の方々が様々な活動を見て知識を共有する場となり、非常に良かったと思います。現在、ブランドを考えるうえで、社会課題として SDGs を考えられると思いますが、今日はそれ以外の観点として『Z 世代』というキーワードについてお話しします。
私の大学のゼミ生が参加している商品開発コンペがあり、ここ数年、その企業の課題は SDGs がトレンドでしたが、最近は Z 世代をキーワードにするケースが非常に多くなっています。例えば先日、大学の学園祭で『へべす』という宮崎県の特産品を商品化するためにゼミ生でアイデアを出しあったとき、アクセサリーにしようという生徒がいました。へべすは種がないので断面が美しいため、樹脂で固めて、世界で一つだけのアクセサリーを作ろうというわけですね。このような我々と違う新しい概念を持っている Z 世代に、どういうものが“刺さる”のかを考えてブランディングすると、新しい局面を迎えることができるかなと思い、本日お話をさせていただきました」