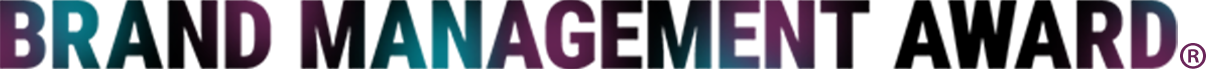REPORT開催レポート
第10回公開シンポジウム
- 開催日
- 2022年11月12日(土)13:00‐17:30
- 場所
- 東京国際フォーラム
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、2022 年 11 月 12 日、東京国際フォーラムにて、第 10 回公開シンポジウムを開催しました。会場約 190 名、オンライン約 130 名、計約 320 名の方に参加していただいた今回のシンポジウムでは、基調講演やコンテストで選ばれた実践事例の発表、トークセッションなどを行いました。
開会の挨拶
最初に岩本俊幸代表理事が次のように挨拶しました。
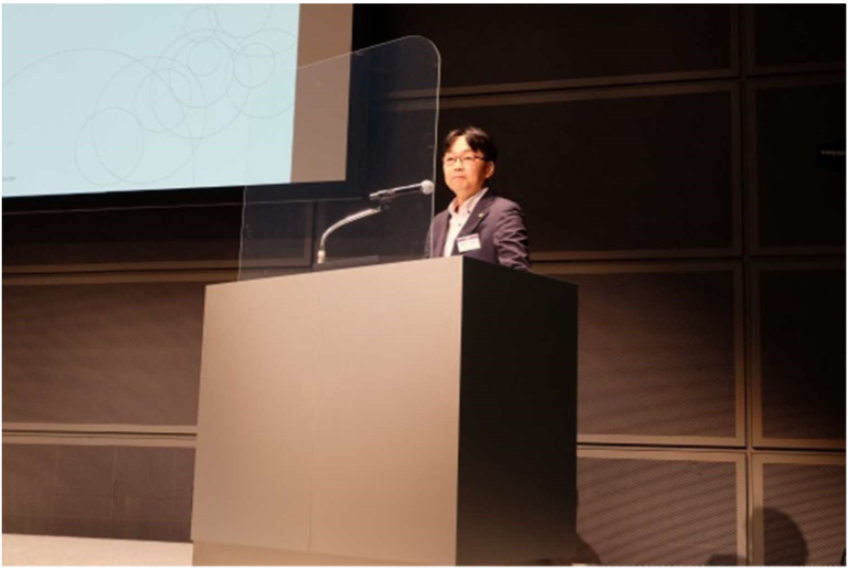
「本日は、第 10 回公開シンポジウムにご参加いただきありがとうございます。2019 年に第 9 回を開催して以来、ようやく 3 年ぶりに開催できることになりました。
当協会は、ブランド価値向上を担う人材育成の専門機関として、設立当初より 3 つの基幹講座を開講し、延べ 3,300 名以上の方に受講していただいております。「ブランディングで社会を良くし、日本を元気にする」というビジョン、ミッションの実現を目指し、仲間を増やしている状況です。
当協会は2010年に一般財団法人格を取得し、通常の講座はもとよりイベント、セミナー、勉強会も多く実施してまいりました。中でもシンポジウムは 2010 年から 2019 年まで毎年開催し、第 5 回からはブランディング事例コンテストの授賞式とプレゼンの機会を設けております。
当協会の講座受講者によるブランディング事例は受賞企業以外にも数多くあり、現在も着実に増え続けております。このような実践事例が多くあるということは、協会で提供するカリキュラムが単なる机上の道具ではなく、現場で活用でき、再現性の実証がなされているからではないかと、回を重ねるごとに強く実感しております。これらの成果は協会トレーナー、講座修了生のみなさまの努力の賜物であり、関係者のみなさまのご支援に改めて感謝申し上げます」
当協会フレームワーク講座のご案内
次に、当協会認定エキスパートトレーナーの守山菜穂子氏が「15 分で分かる!『ブランディング』ミニ講座」と題して講演しました。
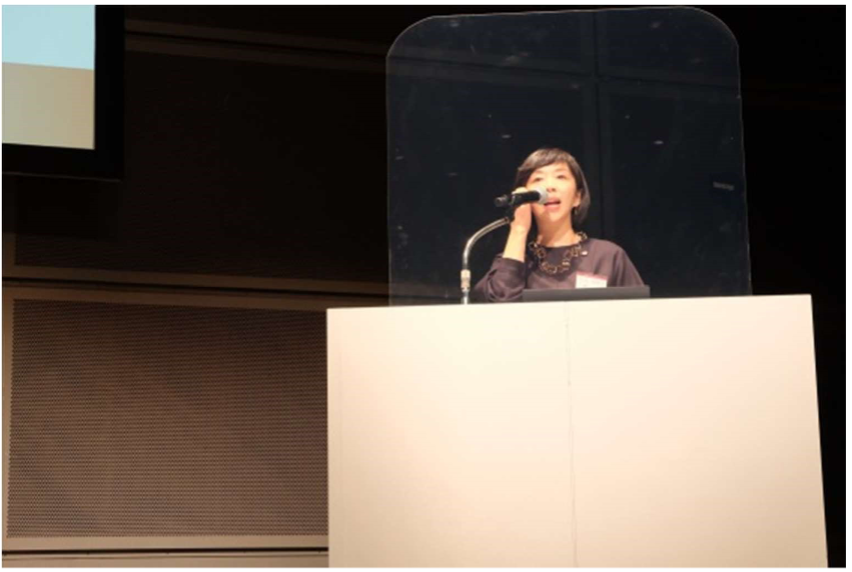
守山氏は、まずブランディングの定義について説明。「企業がブランド・アイデンティティという旗印を立て、それを見た消費者にブランド・イメージができ、これらを一致させることがブランディング」とブランドの基礎について述べ、具体的な手法として、当協会が提唱しているブランド構築の『型』である 8STEP やブランド戦略ピラミッドなどについて解説。「ブランディングとは小手先のものではなく、経営理念に基づいている経営の根幹にあるもの」と自身の考えを語りました。
さらに守山氏は、ブランディングのコツと題して、ブランディングを学ぶことで他社ブランドの仕掛けが分かるようになると指摘。また「ブランディングは一過性ではなく、長期的に売れ続ける仕組みを築くもの」であると伝え、最後に「自社の限られた資源を最大限に生かし、消費者、顧客と自社の喜びを、築きあげましょう」と呼びかけ、締めくくりました。
基調講演「なぜ企業はブランドを再構築するのか?」
基調講演では、当協会顧問を務める目⽩⼤学社会学部教授の⻑崎秀俊氏が「なぜ企業はブランドを再構築するのか?」をテーマに講演しました。

長崎氏は、1「リブランディングとは」2「海外におけるリブランディングの実態」3「日本におけるリブランディングの実態」4「総括:日本企業への提言」と 4 つの段階に分けてリブランディングの実態を解説しました。
まず長崎氏は、リブランディングの定義について「利害関係者の心の中にある差別化されたポジションを代表する名前や競合他社とは異なるアイデンティティを新たに構築すること」と説明。また、リブランディングには可視的要素の変更と不可視的要素の変更の 2 方向があることや、企業レベル、事業レベル、製品レベルの 3 つのレベルが存在していることなどを解説しました。さらに先行研究を紹介し、必要なコストやメリット、リスクなどリブランディングにまつわる実態について語りました。
次に「海外におけるリブランディングの実態」として、海外のサイトの検索エンジンを利用した調査結果を公表。リブランディングの駆動要因は「合併・買収」「スピンオフ」「ブランド・イメージ」が 7 割を占めているとし、「IT 通信」「金融保険」「公共事業・エネルギー・建設」が多いという実態を明かしました。続けて国内のリブランディングについての調査・分析結果も報告。企業名を挙げながら、駆動要因は「合併買収」や「ブランド・イメージ」「グループ経営効率化」が多く、業界分布は「製造業」「公共事業・エネルギー・建設」「金融保険」が半数以上を占めていたことなどを説明し、日本では欧米とは逆に、リブランディング前後ではネーミングに類似性がある変更が多いことを指摘しました。さらに今回の分析から得られたリブランディングの見識として、世界的には独立型のネームが増加傾向にあること、日本はブランド・エクイティを重視していること、連結ネームを採用する傾向があることなどを挙げ、海外と日本の比較を解説しました。 最後に長崎氏は、「総括:日本企業への提言」として、ローコンテクスト文化でのコミュニケーションの重要性など、グローバル展開の際に大事にすべき点を指摘。日本型ブランディングが成功するための提言として締めくくりました。
ブランディング事例コンテスト〜事例紹介〜
今年で 6 回目となるブランディング事例コンテストでは、当協会で学んだことを現場で活用した事例を募集し、その中から構築プロセスと成果が優れた事例を表彰しています。一次審査は書類選考で、シンポジウムでは第一部、第二部の二部構成で最終審査となる事例プレゼンテーションが行われました。(受賞事例は「ブランディング事例コンテスト〜審査発表・授賞式〜」に記載)
トークセッション進行:田中洋氏(当協会特別顧問、中央⼤学名誉教授)
トークセッションでは、審査員による発表事例に関するディスカッションを行いました。
各氏の発言の要旨は以下の通りです。
榛沢明浩氏(当協会評議員)
いずれもすばらしい事例で選ぶのが難しく、どの事例が選ばれてもおかしくないと思いました。個人的には、オルバヘルスケア HD の事例は、非常にややこしい背景を知っているうえで話を聞いていたので味わい深いものがありました。非常に実感の湧く内容だったと思います。
⽔野与志朗氏(当協会評議員、⽔野与志朗事務所株式会社代表取締役社⻑)
本当に甲乙つけがたい、どれが選ばれても不思議ではない事例ばかりでした。将来、より世の中が良くなっていくであろうという視点を持った事例が多かったと思います。私自身は、顧客の立場で「これはぜひ買ってみたい」と思ったものを選びました。
印象的だったのは「いちごの庭プロジェクト」の事例。いわば農業で、とても今的でブランディングの領域が広がっている事例だと思います。ジビエの事例「IPU Gibier」も、「こ
んなところにもブランディングの考え方が応用されるのだな」と印象的でした。
徐誠敏氏(当協会アドバイザー、名古屋経済⼤学経営学部准教授)
今日改めて感じたのは、エクスターナルブランディングでもインターナルブランディングでも、企業の経済的、組織的、社会的価値を生み出すための重要な経営資源は「人」だということでした。ものを作り、売り込み、買うのはすべて人。従業員自身が会社のために自発的に動いて貢献できないといけないと思いました。そういう意味で、今回の事例で取り上げられた会社の従業員たちの笑顔はすごく⼤事だと思います。オルバヘルスケア HD の事例でもあったように、インターナルブランディングの根底にあるのは、人間と人間がつながるようなもの。組織内における人間関係、信頼関係、協力関係をまず作っていかないと、真の意味で組織力を高めることは難しく、従業員の幸せを真剣に考えて日頃から従業員に向き合っている経営トップがいないと変革はうまくいきません。トップ自身の根底にある、人間を愛する精神が⼤事だと思いました。
山崎浩人氏(当協会アドバイザー、株式会社 CARTA COMMUNICATIONS ブランド・コンサルタント)
ブランディングの事例は、企業が成⻑した実績もさることながら、お客や社員の方たちが元気になっているんだろうな、と実感できるものが多いので、今回もそういう点を⼤事にして審査させていただきました。
前回と今回のシンポジウムの最⼤の違いは、やはりコロナの影響だと思います。ポイントは逆転の発想。事例でいくつかありましたが、人が外に出られなくなり、自分たちの立ち位置でやれることに限界を感じる中で、ブランドの本質的な強みを振り返りながら、どのように逆転の発想で持っていくかが見受けられたことが印象に残りました。ブランドのスキルだけではなく、タフさも感じられる回だったと思います。
高田敦史氏(当協会アドバイザー、A.T.Marketing Solution 代表)
今回発表されたみなさん、ここに来られたみなさんがブランドの伝道師として、これから日本の社会をブランドで元気づけてほしいと感じられたプレゼンでした。
個人的には、ぺんてるの事例にいろいろ感じるところがありました。私も 7 年前までトヨタ自動車におり、レクサスブランドなどを中から変えていく活動をしていましたが、中を変えようとするときには 2 種類の人がいます。ひとつは「俺は聞いていない族」、もうひとつは「そうは言っても族」です。こういう人たちに理解してもらい、社内を変えていく活動をされたことに、非常に感銘を受けました。
田中洋氏(当協会特別顧問、中央⼤学名誉教授)
印象に残ったのは、まず doushi 清⽔章充さんの事例「弁理士事務所の法人化に伴うブランディング」です。専門性のあるエキスパートのブランディングというのは、今後ますます注目されていくと思いました。次にコムデザインラボ高木純さんの事例「信州松本エリアの観光プロモーション事業のブランディング」の「#まつもトコトコ」。スマホを使ってうまくナビゲートする仕組みで、松本というもっと注目されていい観光地を開発された試みだったと思います。Sales Lab 伊奈里沙子さんの「スタートアップ企業のリブランディング」は、インサイドセールスという しい業種をクローズアップされたことが非常に興味深かったです。エイドデザイン渡部直樹さんの「 規分譲地開発におけるブランディング」は、不動産の事例は今回が初めてだと思いますが、こういう業種でもブランディングが応用できるんだと印象に残りました。德永美保さんの「高末株式会社のブランディング」も物流企業のブランディングで、これまであまり登場していなかった非常に中身の面⽩い
ビジネスモデルでした。非常に充実した 11 の事例を勉強することができ、今後も引き続き
みなさんに頑張っていただいて、またいろいろな事例を蓄積できればと思います。
また、当協会評議員でクリエイティブハウス R-3 代表の小池玲子氏からのメッセージを田中特別顧問が代読しました。内容は以下の通りです。
小池玲子氏(当協会評議員、クリエイティブハウス R-3 代表)
それぞれ力のこもったすばらしいプレゼンテーションで、⽔準が高かったと思います。感銘を受けました。価値観が激変するこの時代、ブランドの成功の源は、そのブランドが人の心にどう影響を及ぼし、行動に移させるかにあると思います。そのため、そのブランドが人の心にどんな光を投影するかがポイントになってきます。その部分を考えられた方の事例を選びました。

ブランディング事例コンテスト〜審査発表・授賞式〜
今回発表された事例の中から、2022 年は以下の企業に各賞が贈られました。⼤賞、準⼤賞は、今回初の試みとなる参加者による全員投票で決定しました。
・⼤賞:理容室 OTOKO DESIGN のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 OICHOC 八幡清信氏)
・準⼤賞: 規分譲地開発におけるブランディング
(ブランド・マネージャー:エイドデザイン 渡部直樹氏)
・中小企業庁⻑官賞:IPU Gibier のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社ファーストデコ 扇野睦⺒氏)
・日本弁理士会会⻑賞:理容室 OTOKO DESIGN のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 OICHOC 八幡清信氏)
・優秀賞:オルバヘルスケアホールディングス株式会社のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社アイディーエイ 猪子あい音氏/山田祥氏)
・優秀賞:高末株式会社のブランディング
(ブランド・マネージャー:德永美保氏)
・優秀賞:ぺんてるらしさを追求するブランディング
(ブランド・マネージャー:ぺんてる株式会社 田島宏氏)
・地方創生 審査員特別賞:信州松本エリアの観光プロモーション事業のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社コムデザインラボ 高木純氏)
・農商工連携 審査員特別賞:株式会社おさぜん農園のブランディング
(ブランド・マネージャー:シュンビン株式会社 久保貴裕氏)
・農商工連携 審査員特別賞:株式会社九重雑賀のブランディング
(ブランド・マネージャー:有限会社 TTDESIGN 坪田有希子氏)
・奨励賞:スタートアップ企業のブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 Sales Lab 伊奈里沙子氏)
・奨励賞:弁理士事務所の法人化に伴うブランディング
(ブランド・マネージャー:株式会社 doushi 清⽔章充氏)
・SDGs 審査員特別賞: 規分譲地開発におけるブランディング
(ブランド・マネージャー:エイドデザイン 渡部直樹氏)
⼤賞、準⼤賞の発表の要旨は以下の通りです。
⼤賞 理容室 OTOKO DESIGN のブランディング
理容室「OTOKO DESIGN」のブランディングは、埼玉県 座市の理容室「ヘアーサロン寿」が立ち上げたブランドの事例です。理容業界は低賃金・低単価化が著しく、人手不足が深刻化しているのが現状で、寿もブランディング前の 規採用数は年間 0 人、客層は 6 割が 60 代以上の高齢者、95%が既存顧客という状況でした。そのため、先代の築いてきた文化と後継者の思いを生かしたブランディング求められていました。

まずはインターナルブランディングに着手。チーフデザイナーの二代目を中心にチームブランディングを実施し、ヘアスタイリスト、広報担当者、経営者などが一丸となって意見を出し合いました。また、経営理念を見直し、3C 分析などブランド・マネージャー認定協会のステップを活用していく中で、寿がロサンゼルスへの定期的な社員旅行で最先端のヘアデザインを直輸入していることに着目。オンリーワンの魅力が「オトコを上げてくれるデザインセンス」であることに気づき、ブランド・アイデンティティは「自分ブランドを高め、プレミアムな男を作る洗練されたデザイナー」に決定しました。ペルソナは「美意識が高い 40 代経営者」とし、ブレのないブランド作りを実施。さらに従業員のモチベーションアップのため等級評価制度を見直して役職名を再定義し、「デザイナー」の名称を積極的に採用しました。
エクスターナルブランディングでは、ブランド要素、ブランド体験を設計。「ヘアーサロン寿」というショップブランドは生かしつつ、サービスブランドとして「OTOKO DESIGN」を立ち上げ、ロゴを作り、商標も取りました。さらに理容師の刈り上げ技術とアイロンパーマが最⼤限生かせるロサンゼルス直輸入の「FADE カット」を全面的にプッシュ。ブランドコンセプトを基に、一貫したアウトプットを設計し「オトコを上げろ。」というキャッチコピーを作り、ウェブサイトをリニューアルし、内外装に手を加え、父の日に合わせた
SNS プロモーションも実施しました。 これらのブランディングにより、売り上げはコロナ前の 2018 年と比較して 170%アップを達成。カットメニューの料金を 184%値上げしたにもかかわらず、年間顧客数は 700 人アップ。顧客単価は 154%アップし、スタッフ数も 160%アップを実現しました。今後は、
2023 年に 2 店舗目のオープンを予定。さらに 2032 年までに直営 5 店舗、ロサンゼルス 1
店舗を目指しているなど、「OTOKO DESIGN」はたな挑戦を始めています。
準⼤賞 規分譲地開発におけるブランディング
「Link Ring Town Kurusu(リンク・リング・タウン栗栖)」は、地元の和歌山県で宅地開発分譲事業、不動産事業、ガーデンエクステリア事業を展開しているイエステージグループが行った宅地開発分譲事業の事例です。同グループが小規模な分譲地にもかかわらず、このような街づくりを推進しているのは、和歌山県に人口の減少、若者の流出、自然災害という 3 つの問題があるためです。そこで同グループは「若者が帰ってきたくなるような、災害に強い魅力的な街を作ること」を着想し、3 つの問題にアプローチしようと考えました。

同グループでは、災害に強い魅力的な街とは「住み続けられる街」であり、そのためにはコミュニティーの形成が必要だと考えました。なぜならコミュニティーが良質であれば、災害時にも⼤きな役割を果たすからです。そこで同グループでは「価値観の近い人を集めれば良質なコミュニティーが形成され、いざというときに助け合える、災害時にも強い持続可能な街を作ることができる」と仮説を立て、ブランドを構築。
その結果、防災と街並み形成をテーマにした「あそぶ、たのしむ、つながる セーフティーな街」というブランド・アイデンティティができました。このブランド・アイデンティティに沿って「グリーンでつなげる一体感のある街並み」「建築協定によって守られる美しい街並み」「楽しみながら育まれるコミュニティー」という 3 つのコンセプトを打ち立て、コンセプトを明確に打ち出すことで
「こんな街に住んでみたい」と思う、価値観の近い人を集めたのです。
こうしたブランディングにより、2023 年 2 月と定めていた完売目標よりも早い段階での完売が見込まれているなど、早々にマーケティング目標を達成。また、問い合わせの質が変化したほか、以降のプロジェクトにおいてはスタッフが自発的に動くなど、スタッフの行動変容という成果が顕れています。
閉会の挨拶
最後に田中洋特別顧問から次のような閉会の挨拶がありました。 「今日は⼤変充実した一日を過ごさせていただきました。素晴らしい 11 の事例があり、それ以外にもいろいろな応募があって、注目すべき事例がたくさん集まったと思います。中身も非常に充実していたと思いました。⼤賞に選ばれた『OTOKO DESIGN』のような目を引くデザインやブランドの設計があり、業種は、食品はもちろん農業、不動産など、これまでコンテストであまり目にしなかったものまで広がっておりました。手法もインターナルブランディングの手法を駆使したり、テクノロジーを使った手法が発達していたり、非常に高いレベルの争いになっている事例コンテストで、楽しませていただきました。今回は 3 年ぶりの対面での会合が実現し、またみなさんにお会いできたこともうれしい一日でした。また来年、ぜひ事例コンテストを中心に、シンポジウムにご参集いただきたく思っておりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。改めて、入賞されたみなさん、おめでとうございました。今日はありがとうございました」